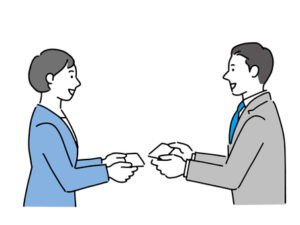【難病の方へ】就労継続支援B型の選び方|安心して通える事業所探しの3つのポイント
難病を抱えながら「社会とつながりを持ちたい」「少しでも働きたい」という気持ちと、「体調が不安で、一般の会社で働くのは難しい」という気持ちの間で、悩んでいませんか?
そのように感じている方にとって、就労継続支援B型事業所は、ご自身の体調やペースを最優先にしながら、働くことを通して社会参加を目指せる大切な場所です。
しかし、「難病でも利用できるの?」「どんな事業所を選べばいいの?」といった疑問や不安も多いかと思います。
この記事では、難病のある方が、自分に合った就労継続支援B型事業所を安心して選べるように、利用できる条件や選び方、利用までの流れなどをわかりやすくまとめています。
難病の方も利用できる福祉サービス・就労継続支援B型事業所とは?

まず初めに、「就労継続支援B型事業所」(以下B型事業所)がどのような場所なのかを解説します。
障害や難病のある方が、自分の体調やペースに合わせて、無理のない作業に取り組み、その作業に応じて工賃を受け取ることができる福祉サービスです。
一番の特徴は「雇用契約を結ばない」点にあり、出勤日数や作業時間に厳しい決まりがありません。
週1日や1日数時間からの利用も可能な事業所が多く、体調が優れない日には無理せず休むことができるなど、柔軟な働き方ができるのが魅力です。
📝関連記事はこちら
【初心者向け】就労継続支援B型とは?制度の概要と失敗しない選び方ガイド
難病があっても働ける!就労継続支援B型で安心して仕事を始める方法
発達障害と就労継続支援B型の関係について、いっしょに考えてみませんか?
難病の方の対象条件・どんな人が利用できるの?

「難病でも利用できるの?」という疑問は、多くの方が抱く不安だと思います。
結論から言うと、難病の方も対象となります。
就労継続支援B型の対象者は、具体的に以下のような方々とされています。
重要なのは、必ずしも障害者手帳を持っている必要はないという点です。医師の診断書や定期的な通院の事実など、「障害や病気によって一般就労が困難である」と自治体(市区町村)が判断すれば、サービスの利用対象となります。
厚生労働省が定めるB型事業所の対象者は、具体的に以下のような方々です。



アセスメントとは?
アセスメントとは、ある対象の状態や特性を評価・分析することを指します。
就労継続支援B型の分野では、利用者の能力や適性、課題を把握し、最適な支援方法を決めるために行われます。
厚生労働省が定めるB型事業所の対象者は、具体的に以下のような方々です。



アセスメントとは?
アセスメントとは、ある対象の状態や特性を評価・分析することを指します。
就労継続支援B型の分野では、利用者の能力や適性、課題を把握し、最適な支援方法を決めるために行われます。
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に問い合わせてみることが第一歩です。
📝参考リンク(外部)
📝関連記事はこちら
【知らないと損!】就労継続支援B型は「手帳なし」で利用OK!受給者証があれば働き方改革が始まる!
【最重要】難病の方がB型事業所を選ぶための3つのポイント

ここからは、この記事の核心である「選び方」について、難病の方が特に重視すべき3つのポイントを解説します。
ポイント1:体調への配慮と柔軟な支援体制を確認する
難病の方は日によって体調の波があることが多いため、事業所の支援体制がご自身の状況に合っているかが最も重要です。
見学や相談の際には、以下の点を必ず確認しましょう。
- 休憩の取りやすさ: 体調に合わせて、自分のタイミングで休憩を取れるか。
休憩スペースは確保されているか。 - 通院への配慮: 定期的な通院や、急な体調不良による早退・欠席に柔軟に対応してもらえるか。
- 作業環境: 空調は快適か、座り仕事が中心か、車椅子での移動はスムーズかなど、身体的負担が少ない環境か。
- 在宅ワークの可否: 事業所によっては、在宅での作業を認めている場合があります。
通所が困難な日でも作業ができる選択肢があるかは大きなポイントです。 - 相談体制: 病気のことや体調の不安を気軽に相談できるスタッフ(サービス管理責任者など)がいるか。
ポイント2:無理なく続けられる仕事内容か見極める
B型事業所では、色々な種類の仕事があります。
ご自身の体力や病状、そして興味関心に合った仕事内容かを見極めましょう。
【B型事業所の主な仕事内容の例】
軽作業
部品組立、検品、シール貼り、袋詰め、箱折り など
PC作業
データ入力、文字起こし、簡単なWebサイト更新 など
創作・製造
パン・お菓子の製造販売、アクセサリーや雑貨の制作、木工 など
農作業
野菜の栽培、収穫、袋詰め など
体力に自信がない方は座ってできる軽作業やPC作業、手先を動かすのが好きな方は創作活動など、自分の「できること」「やりたいこと」と照らし合わせて、無理なく楽しく続けられそうな事業所を選びましょう。
ポイント3:事業所の雰囲気と「通いやすさ」をチェックする
制度や仕事内容が合っていても、事業所の雰囲気が合わなければ通い続けるのは難しくなります。
見学・体験利用を必ず行う
ホームページやパンフレットだけでは分からない、実際の雰囲気を肌で感じることが大切です。
スタッフや他の利用者さんの表情、コミュニケーションの様子などを観察しましょう。
物理的な通いやすさ
自宅からの距離や交通手段も重要です。
送迎サービスの有無も確認すると良いでしょう。
精神的な通いやすさ
スタッフの対応は丁寧か、利用者同士の人間関係は良好そうかなど、「ここなら安心して過ごせそう」と思えるかが最終的な決め手になります。
複数の事業所を見学・体験して、じっくり比較検討することをおすすめします。
📝関連記事はこちら
利用までの流れ – 安心の5つのステップ

実際にB型事業所を利用するまでの大まかな流れを、ステップ形式で解説します。
- 【STEP 1】相談
- お住まいの市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に「B型事業所を利用したい」と相談します。
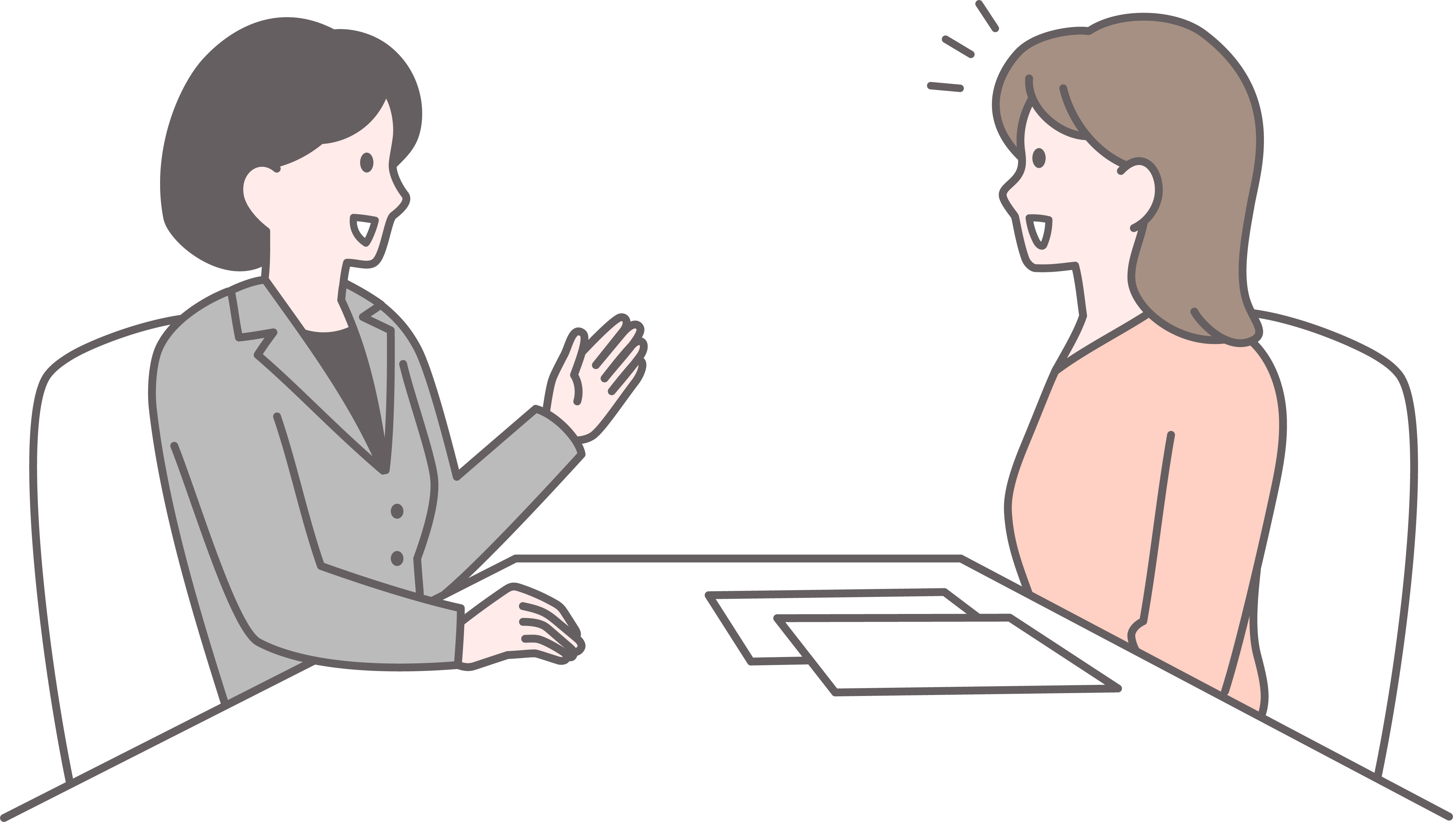
- 【STEP 2】事業所の見学・体験
- 気になる事業所をいくつか見学・体験し、自分に合う場所を探します。

- 【STEP 3】利用申請
- 利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口でサービスの利用申請を行います。この際、医師の診断書などが必要になる場合があります。

- 【STEP 4】サービス等利用計画の作成と受給者証の交付
- 相談支援専門員と一緒に、どのような支援を受けるかの計画(サービス等利用計画案)を作成し、提出します。
その後、市区町村から「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
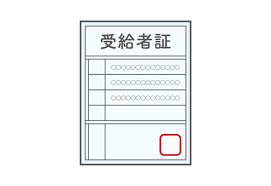
- 【STEP 5】事業所との契約・利用開始
- 受給者証を持って事業所へ行き、利用契約を結びます。
これで、いよいよ利用開始です。

📝関連記事はこちら
就労継続支援B型とは?制度の仕組みから利用方法まで分かりやすく解説
【最新版】就労継続支援B型の利用料はいくら?無料になる条件・実際の費用をわかりやすく解説
よくある質問(FAQ)
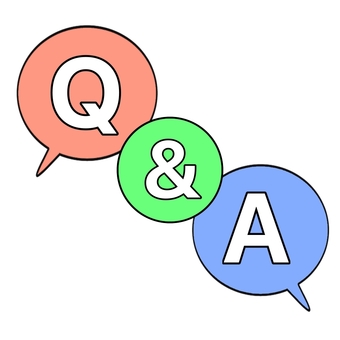
最後に、難病の方がB型事業所を検討する際によくある質問にお答えします。
-
障害者手帳がないと利用できませんか?
-
いいえ、必ずしも必要ではありません。
医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証など、障害や疾病の状況が分かり、市区町村が必要性を認めれば利用可能です。
まずは窓口でご相談ください。
-
工賃はどのくらいもらえますか?
-
工賃は、生産活動から得られた収益から経費を差し引いた額を利用者に分配する仕組みです。
そのため、金額は事業所や作業内容、個人の作業時間によって大きく異なります。
厚生労働省の令和4年度の調査によると、月額の全国平均工賃は17,031円です。
工賃の額も大切ですが、それ以上に安心して通える環境かどうかを重視することをおすすめします。
-
週に何日から利用できますか?体調が悪い日は休めますか?
-
多くのB型事業所では、週1日・1日数時間からなど、ご自身のペースで利用を開始できます。
もちろん、体調が悪い日は無理せず休むことができます。
利用開始前に、どれくらいのペースで通いたいかを事業所に相談してみましょう。
-
A型事業所や就労移行支援との違いは何ですか?
-
簡単に言うと、目的と働き方が異なります。
- B型事業所: 雇用契約なし。体調に合わせて働く場所。作業に応じて工賃を受け取ることができる。
- A型事業所: 雇用契約あり。最低賃金が保障されるが、事業所で定められた勤務が必要。
- 就労移行支援: 雇用契約なし。一般企業への就職を目指すための訓練の場所(原則2年間)。
ご自身の現在の体調や「どうなりたいか」という目標に合わせて選ぶことが大切です。
📝関連記事はこちら
【完全ガイド】就労継続支援B型のメリットとは?自分らしい働き方を実現する方法
就労継続支援B型の工賃・収入ガイド|働き方と生活の安定を徹底解説
就労継続支援B型と就労移行支援を徹底比較!自分に最適な支援を見つけよう!
📝参考リンク(外部)
【2025年最新】就労継続支援A型とは?対象者・仕事内容・利用方法を完全解説 | 就労継続支援事業所 | トライアングル
【まとめ】
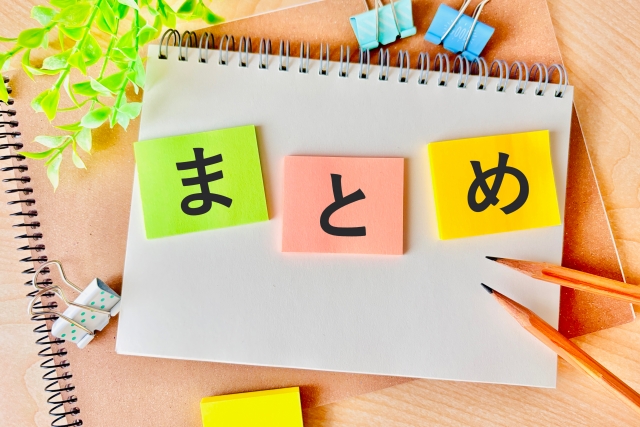
B型事業所は、難病を抱える方がご自身のペースを大切にしながら、社会とのつながりや働く喜びを感じられる貴重な選択肢です。
重要なのは、一人で抱え込まず、「体調への配慮」「無理のない仕事内容」「事業所の雰囲気」という3つのポイントを軸に、自分に合った事業所をじっくり探すことです。
この記事を参考に、まずは一歩、お住まいの地域の相談窓口や、気になる事業所の見学に足を運んでみてはいかがでしょうか。
あなたに合った、安心して通える場所がきっと見つかるはずです。
📝関連記事はこちら
就労継続支援B型事業所の選び方完全ガイド|失敗しない8つのポイントと就労移行支援との徹底比較
📝 参考リンク(外部)
就労継続支援B型事業所一覧 – 障がい者就労支援情報~全国版~
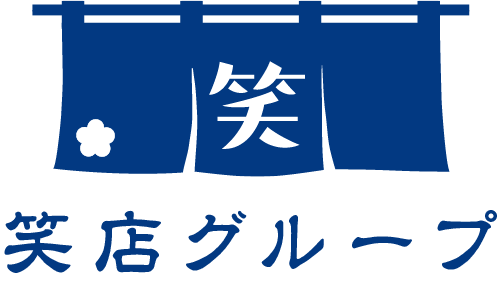
就労継続支援B型事業所「笑店グループ」では、「自分らしく働きたい」という気持ちを大切にする、あなたのための場所です。
就労継続支援の制度や特徴はもちろん、利用の対象となる方、そして利用にあたっての疑問など、皆様にとって役立つ情報を丁寧にご紹介しております。
「まずは少しずつ」「自分のペースで続けたい」
そんな思いをお持ちの皆様にも、安心して通っていただける温かい環境をご用意しています。
利用者様お一人ひとりの「やってみたい」を尊重し、それぞれのペースに合わせた働き方をサポートいたします。
対象となる方について
知的障害、精神障害、身体障害、発達障害、難病をお持ちの方で、一般企業での就労に不安がある方、または就労移行支援事業などを利用したが就労に結びつかなかった方などが対象となります。
お仕事内容について
利用者様の多様なニーズに合わせて、パソコンやスマートフォンを使った様々なお仕事をご用意しています。
ご自身のスキルや興味に合わせて、無理なく取り組める作業がきっと見つかります。
在宅ワークも可能!
お仕事内容によっては、ご自宅にいながら働く「在宅ワーク」も可能です。
通所が難しい方でも、社会との繋がりを持ちながら、ご自身のペースで働くことができます。
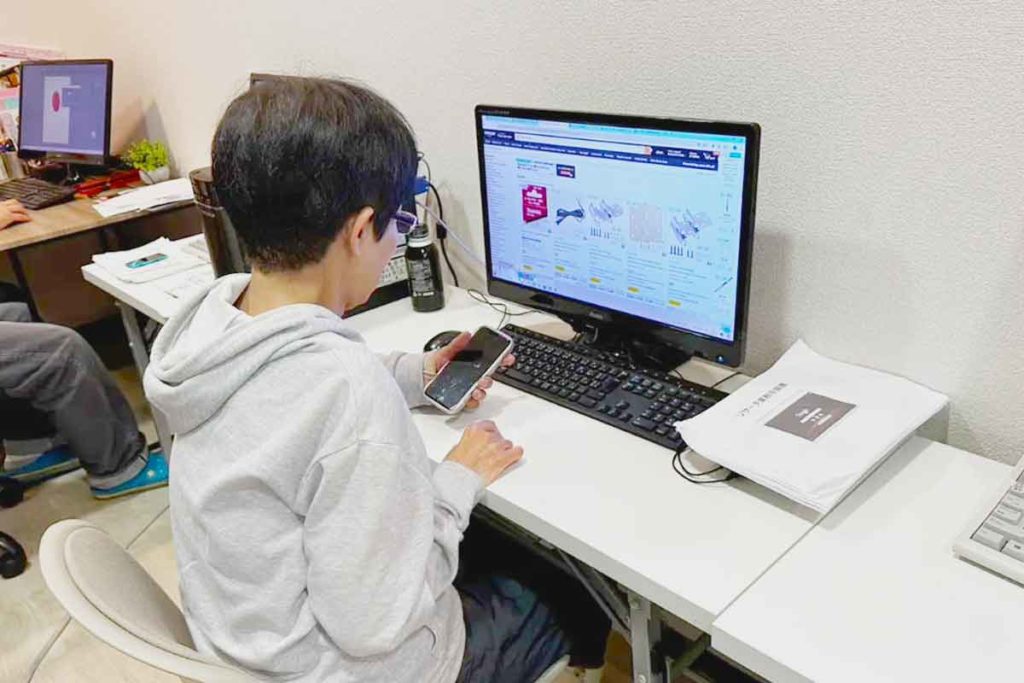
※当事業所では内職の在宅は行っておりません。
「もしかしたら、自分にもできるかも!」
そう感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたが「自分らしく働ける」ためのサポートがここにあります。
安心できる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

どんなことでもお気軽にご相談ください。
スタッフが一人ひとり丁寧に対応させていただきます。


事業所のご案内
🏢 就労継続支援B型事業所 ふじのもり笑店(旧たきがわ笑店)
📮 住所
〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町839-14
ソフトウェーブビル3階
📞 電話番号
075-644-4815
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・祝日除く)
📧 メール
infoshoten-group.com
🌐 公式サイト(HP)
📱 SNS
🚶♂️ アクセス
京阪本線「藤森駅」西口より徒歩3分
ソフトウェーブビルのエレベーターで3階までお越しください。
🏢就労継続支援B型事業所 ふるかわばし笑店
📮 住所
〒571-0030
大阪府門真市末広町1番7号
末広ビル2階(旧松井ビル)
📞 電話番号
050-1506-9415
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚶♂️ アクセス
京阪本線「古川橋駅」より線路沿いに東へ徒歩4分
末広ビル(旧松井ビル)階段で2階までお越しください。

📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)
🏢就労継続支援B型事業所 たけだ笑店
📮 住所
〒612-0028
京都府京都市伏見区竹田段川原町269番地
📞 電話番号
050-1113-9161
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚃 アクセス
京都市営地下鉄・近鉄「竹田駅」北口より徒歩3分
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)