知らないと損!B型×自立支援医療の活用ポイント徹底ガイド

B型事業所を利用したいけど、
自立支援医療のことも関係あるって聞いて…
…正直、よく分からなくて不安。
手続きとか難しそうで、自分にちゃんとできるのかなぁ。

制度の名前は聞いたことあるけど、
どうやって使うのか全然分からない。
損しないように、ちゃんと知っておきたいけど、
どこから調べればいいのか迷っちゃうな…。
障がいと共に「自分らしく働きたい」「安定した生活を送りたい」と願うあなたへ。
就労継続支援B型と自立支援医療受給者証は、その願いを現実にするための強力なサポートシステムです。
多くの人が「よく分からない」「手続きが複雑そう」と感じがちですが、これらを理解し、活用することで、あなたの未来は大きく変わります。
この記事では、それぞれの制度の基本から、知っておくべき手続き、そしてあなたの生活にどう役立つのかを、徹底的にわかりやすく解説します。
さあ、一歩踏み出すための知識を、ここで手に入れましょう。
1. 就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型事業所は、障がいや難病を持つ方が自分のペースで働くことをサポートする福祉サービスです。
一般企業での就労が困難な方や、雇用契約を結んで働くことが難しい方を対象に、軽作業などの訓練機会を提供し、最終的にはA型事業所への移行、また一般就労への移行など、地域生活における自立を目指します。
主な目的は以下の通りです。
B型事業所の目的
- 働く喜びの提供: 自分のペースで働き、達成感を得る機会を提供します。
- 社会参加の促進: 地域社会との繋がりを深め、孤立を防ぎます。
- 生活リズムの確立: 規則正しい生活習慣を身につけ、健康的な毎日を送れるよう支援します。
- スキルアップ: 作業を通じて様々なスキルを習得し、自信をつけます。
B型事業所での作業内容は多岐にわたります。
例えば、以下のようなものがあります。
一般的な作業内容
- 内職作業(部品の組み立て、検品、袋詰めなど)
- 清掃作業
- データ入力
- カフェやレストラン等での調理補助、接客
- 農作業
- ハンドメイド品の製作、販売

笑店グループでは、利用者様一人ひとりのニーズに合わせ、パソコンやスマートフォンを活用した多様なお仕事をご用意しています。
スキルや興味に応じて、無理なく取り組める作業を見つけていただけます。
作業を通じて得られる工賃は、最低賃金の適用外ですが、働くことへのモチベーション維持や、生活費の一部に充てられます。
📝関連記事はこちら
精神障害を持つ方へ|就労継続支援B型事業所で安心して働ける環境・サポートを徹底解説
障害者手帳のメリットを徹底解説!就労継続支援B型事業所で新たな一歩を踏み出そう
2. 自立支援医療受給者証とは?

自立支援医療受給者証は、特定の精神疾患や身体の障がいを持つ方が、医療費の自己負担額を軽減するための制度です。
医療費の自己負担割合が原則1割に軽減され、さらに所得に応じて月額の上限額が設定されます。
2.1. 制度の目的
この制度の目的は、障がいを持つ方が継続的に必要な医療を受けられるようにし、症状の悪化を防ぎ、社会生活への復帰や維持を支援することにあります。
特に精神疾患の場合、継続的な治療が重要であり、医療費の負担が治療継続の妨げにならないように配慮されています。
2.2. 対象となる疾患・状態
- 精神通院医療: うつ病、統合失調症、発達障がい、てんかんなどの精神疾患で通院治療が必要な方。
- 更生医療: 身体障がい者手帳をお持ちの方が、その障がいを取り除く、または軽減するための医療が必要な場合。
- 育成医療: 18歳未満の児童で、身体に障がいがあり、その障がいを除去または軽減する手術などの医療が必要な場合。
就労継続支援B型の利用者にとって特に関係が深いのは「精神通院医療」です。
精神疾患を抱えながらB型事業所で働く多くの方が、自立支援医療を利用しています。
2.3. 軽減される医療費の具体例
通常、医療費の自己負担割合は3割ですが、自立支援医療受給者証があれば1割に軽減されます。
さらに、所得に応じた月額上限額が設定されており、例えば以下のような区分があります。
押さえるポイント
- 生活保護世帯: 自己負担なし
- 低所得1・2: 月額2,500円または5,000円
- 中間所得1・2: 月額10,000円または20,000円
- 一定所得以上: 自己負担なし(重度かつ継続の場合)
これにより、高額な医療費が必要な月でも、負担を気にせず治療に専念できる環境が整います。
📝関連記事はこちら
知的障害のある方の「働く」を支える!就労継続支援B型事業所のサポート体制と選び方ガイド
【保存版】知的障害のある方がB型事業所を利用するためのすべて|条件・申請・選び方
(外部リンク)
3. 就労継続支援B型と自立支援医療受給者証の連携

就労継続支援B型と自立支援医療受給者証は、障がいを持つ方の生活を多角的にサポートする上で、非常に重要な連携関係にあります。
3.1. 経済的負担の軽減と就労支援
精神疾患を持つ方が就労継続支援B型を利用する際、通院治療が欠かせないことがほとんどです。
自立支援医療受給者証があることで、通院にかかる医療費の負担が軽減され、経済的な不安を減らすことができます。
これにより、安心してB型事業所での作業に集中し、働くことに前向きに取り組むことが可能になります。
自立支援医療受給者証の活用ポイント
- 医療継続の支援: 医療費の負担が少ないため、治療を中断することなく継続でき、症状の安定に繋がります。
- 生活の安定: 医療費以外の生活費に回せるお金が増え、生活の安定に寄与します。
- 就労への集中: 経済的な心配が減ることで、就労訓練や作業に集中しやすくなります。
3.2. 精神的な安定と作業効率の向上
精神疾患の治療が継続されることで、症状が安定しやすくなります。
症状の安定は、B型事業所での作業効率の向上に直結します。
- 集中力の向上: 症状が落ち着くことで、作業への集中力が高まります。
- 気分の安定: 気分の波が小さくなり、安定して作業に取り組めるようになります。
- 対人関係の改善: 症状の安定は、スタッフや他の利用者とのコミュニケーションを円滑にし、より良い人間関係を築く助けになります。
📝関連記事はこちら
「無理なく働く」を応援|精神障害のある方のためのB型事業所の仕事内容ガイド
【知的障害×就労支援】B型事業所ってどんなところ? 仕事内容から選び方までやさしく解説
4. 申請手続きと利用の流れ

ここからは、実際にこれらの制度を利用するための具体的なステップを見ていきましょう。
「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。
一つ一つの手続きを順を追って解説していきます。
必要な書類や申請の流れを事前に把握しておくことで、スムーズに制度を活用できるようになります。
あなたの「働く」と「治療」を支えるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

自立支援医療受給者証とB型事業所の利用は、どちらも市区町村の窓口がスタート地点になります。
診断書や証明書など必要書類をそろえ、計画→申請→審査→決定という流れを踏む点が共通です。
一度取得・利用が始まっても、期限前の更新手続きが重要なポイント。
制度を正しく理解して準備すれば、手続きは意外とスムーズに進められます。
📝関連記事はこちら
【発達障害の方へ】就労継続支援B型事業所の支援体制とは?自分に合う場所を見つけるポイントを徹底解説
難病と共に働く希望の光:就労継続支援B型事業所で 自分らしい働き方を見つけよう
(外部リンク)
就労継続支援B型を利用するには?手続きの流れをイチから紹介!
5. FAQ:よくある質問

就労継続支援B型と自立支援医療受給者証について、多くの方が疑問に感じる点をQ&A形式でまとめました。
気になる疑問を解消し、より安心して制度を利用するための参考にしてください。
- 自立支援医療受給者証がなくても就労継続支援B型は利用できますか?
-
はい、利用できます。
自立支援医療受給者証は医療費の助成制度であり、就労継続支援B型の利用要件ではありません。
しかし、精神疾患等で通院されている方は、医療費の負担軽減になるため、取得をお勧めします。
- 精神疾患がなくても就労継続支援B型は利用できますか?
-
はい、利用できます。
就労継続支援B型は、精神障がいだけでなく、身体障がいや知的障がいを持つ方も対象となります。
一般企業での就労が困難な理由が精神疾患以外の場合でも、利用を検討できます。
- 自立支援医療受給者証の申請に費用はかかりますか?
-
申請自体に費用はかかりません。
ただし、申請に必要な診断書の作成には、文書料として数千円程度の自己負担が発生する場合があります(自立支援医療の対象外)。
- 就労継続支援B型で得られる工賃はどのくらいですか?
-
工賃は事業所や作業内容によって大きく異なりますが、全国平均では月額1万円~2万円程度とされています。
最低賃金の適用外ですが、働くことへの意欲向上や、生活費の一部に充てることを目的としています。
- 就労継続支援B型から一般就労への移行は可能ですか?
-
はい、可能です。
多くの就労継続支援B型事業所は、利用者が最終的に一般就労へ移行できるよう支援を行っています。
履歴書の書き方指導、面接練習、職場見学、就職先の紹介など、様々なサポートを受けることができます。
- 就労継続支援B型の利用期間に制限はありますか?
-
原則として、就労継続支援B型には利用期間の制限はありません。
ご本人の状況や希望に合わせて、長期的に利用を継続することも可能ですし、一般就労を目指して一定期間利用することもできます。
定期的に、サービス等利用計画の見直しが行われます。

重要なポイントは、就労継続支援B型も自立支援医療受給者証も、
あなたの「働きたい」という気持ちと「安定した生活を送りたい」という願いを力強くサポートするための制度だということです。
制度を活用して安心・充実の毎日を!
- 利用の選択肢は広い: 精神疾患の有無に関わらず、様々な障がいを持つ方がB型事業所を利用できます。
- 医療費の心配を軽減: 自立支援医療受給者証があれば、安心して治療を継続し、症状の安定に繋げられます。
- 将来へのステップアップも可能: B型事業所は単なる働く場ではなく、一般就労への大切なステップにもなります。
- 継続的なサポート: 期間の制限なく、あなたのペースで利用を続けられる柔軟性があります。
これらの制度は、あなたの可能性を広げ、より豊かな毎日を送るための心強い味方となるでしょう。
📝関連記事はこちら
身体障害の種類と就労支援:B型事業所で実現できる働き方とは?
聴覚障害があっても自分らしく働ける!就労継続支援B型事業所の魅力と選び方
6. あなたの「働く」をサポートする制度
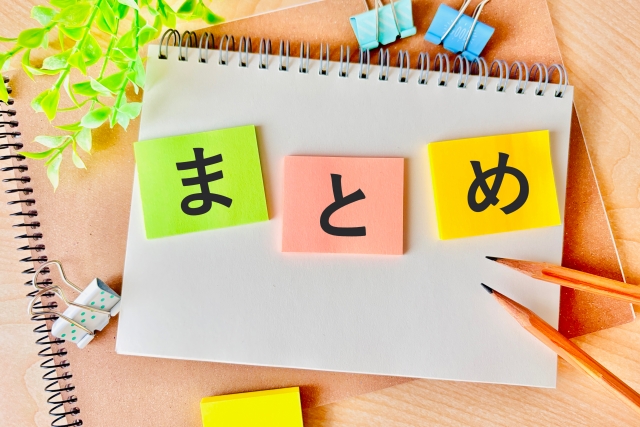
就労継続支援B型と自立支援医療受給者証は、障がいを持つ方が地域で安定した生活を送り、社会参加を実現するための重要な二つの柱です。
この二つの制度を上手に活用することで、あなたは安心して治療を受けながら、自分らしく働くこと、そして豊かな生活を送ることを目指すことができます。
もしご自身の状況に不安や疑問がある場合は、まずは市区町村の障がい福祉担当窓口や、相談支援事業所にご相談ください。
専門のスタッフが、あなたの状況に合わせた最適なサポートを一緒に考えてくれるはずです。
あなたの「働く」をサポートする制度が、ここにあります。
📝関連記事はこちら
【重度知的障害でも働ける!】就労継続支援B型事業所で安心して働く方法とは?
【身体障害のある方へ】就労継続支援B型事業所の選び方|失敗しないための重要ポイント
重度身体障害のある方の「働く」を支える光:就労継続支援B型事業所という選択
統合失調症でも大丈夫!就労継続支援B型事業所で無理なく社会参加する方法
📝 参考リンク(外部)
就労継続支援B型事業所一覧 – 障がい者就労支援情報~全国版~
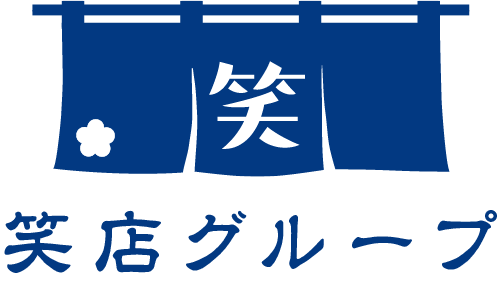
就労継続支援B型事業所「笑店グループ」では、「自分らしく働きたい」という気持ちを大切にする、あなたのための場所です。
就労継続支援の制度や特徴はもちろん、利用の対象となる方、そして利用にあたっての疑問など、皆様にとって役立つ情報を丁寧にご紹介しております。
「まずは少しずつ」「自分のペースで続けたい」
そんな思いをお持ちの皆様にも、安心して通っていただける温かい環境をご用意しています。
利用者様お一人ひとりの「やってみたい」を尊重し、それぞれのペースに合わせた働き方をサポートいたします。
対象となる方について
知的障害、精神障害、身体障害、発達障害、難病をお持ちの方で、一般企業での就労に不安がある方、または就労移行支援事業などを利用したが就労に結びつかなかった方などが対象となります。
お仕事内容について
利用者様の多様なニーズに合わせて、パソコンやスマートフォンを使った様々なお仕事をご用意しています。
ご自身のスキルや興味に合わせて、無理なく取り組める作業がきっと見つかります。
在宅ワークも可能!
お仕事内容によっては、ご自宅にいながら働く「在宅ワーク」も可能です。
通所が難しい方でも、社会との繋がりを持ちながら、ご自身のペースで働くことができます。
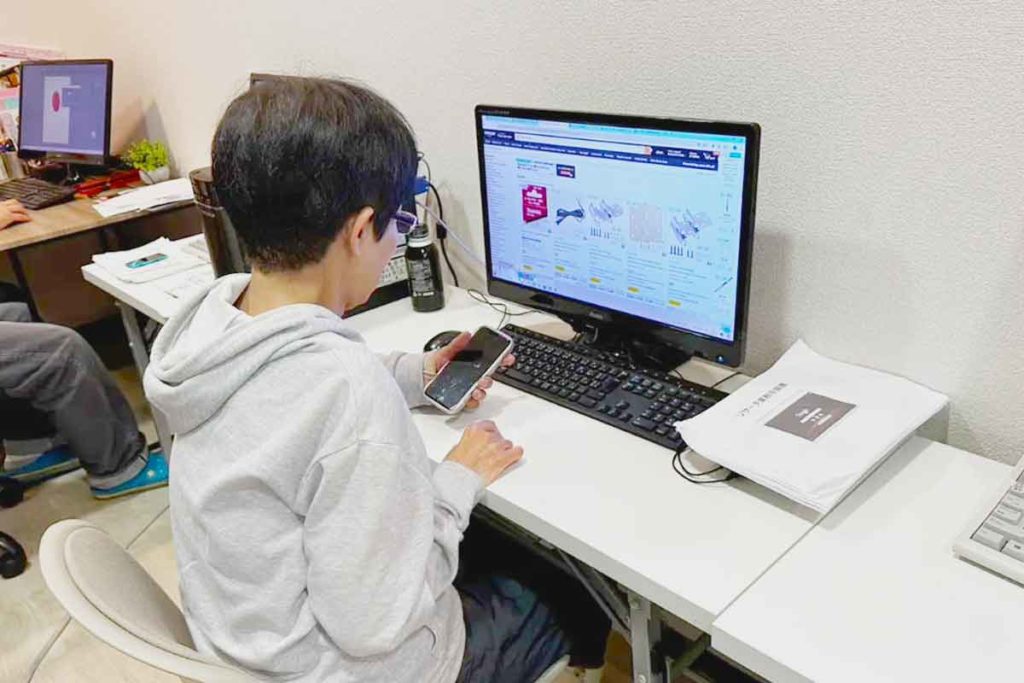
※当事業所では内職の在宅は行っておりません。
「もしかしたら、自分にもできるかも!」
そう感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたが「自分らしく働ける」ためのサポートがここにあります。
安心できる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

どんなことでもお気軽にご相談ください。
スタッフが一人ひとり丁寧に対応させていただきます。


事業所のご案内
🏢 就労継続支援B型事業所 ふじのもり笑店(旧たきがわ笑店)
📮 住所
〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町839-14
ソフトウェーブビル3階
📞 電話番号
075-644-4815
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・祝日除く)
📧 メール
infoshoten-group.com
🌐 公式サイト(HP)
📱 SNS
🚶♂️ アクセス
京阪本線「藤森駅」西口より徒歩3分
ソフトウェーブビルのエレベーターで3階までお越しください。
🏢就労継続支援B型事業所 ふるかわばし笑店
📮 住所
〒571-0030
大阪府門真市末広町1番7号
末広ビル2階(旧松井ビル)
📞 電話番号
050-1506-9415
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚶♂️ アクセス
京阪本線「古川橋駅」より線路沿いに東へ徒歩4分
末広ビル(旧松井ビル)階段で2階までお越しください。

📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)
🏢就労継続支援B型事業所 たけだ笑店
📮 住所
〒612-0028
京都府京都市伏見区竹田段川原町269番地
📞 電話番号
050-1113-9161
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚃 アクセス
京都市営地下鉄・近鉄「竹田駅」北口より徒歩3分
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)


