【保存版】知的障害のある方がB型事業所を利用するためのすべて|条件・申請・選び方
知的障害のあるお子さんやご家族にとって、「働く」ということは希望であると同時に、多くの不安が伴うテーマかもしれません。

うちの子は知的障害があるけれど、B型事業所のような場所で働けるのだろうか?

利用するにはどんな条件が必要?療育手帳は絶対にないとダメ?

どうやって手続きを進めればいいのか、手順がわからなくて不安…
このようなお悩みを抱えて、一歩を踏み出せずにいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご安心ください。
B型事業所は、知的障害のある方が自分らしいペースで働き、社会と繋がるための大切な場所です。
この記事では、知的障害のある方が就労継続支援B型を利用するための受け入れ条件を中心に、療育手帳の必要性、利用開始までの具体的なステップ、そしてご本人に合った事業所の選び方まで、
専門的な情報を誰にでも分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、B型事業所利用への不安が解消され、次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えているはずです。
就労継続支援B型事業所ってどんなところ?

まずはじめに、「就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)」とはどのような場所なのか、わかりやすくご説明します。
B型事業所は、障害や難病のある方が雇用契約を結ばずに、自分の体調や生活リズムに合わせて無理のない範囲で働ける福祉サービスです。
行う作業は、封入や袋詰め、軽作業、農作業、手芸、清掃、リサイクルなど、事業所によってさまざま。
作業の結果に応じて「工賃」というかたちで報酬が支払われます。
企業などでの一般就労がむずかしい方でも、「働くことの楽しさ」や「できた!という達成感」を感じながら、社会とのつながりや生活リズムを整えることができる場所です。
また、職員のサポートのもとで、日常生活の相談支援やスキルアップのサポートも受けられます。
知的障害のある方にとっても、安心して通える場所として、日中の活動の場や社会参加のきっかけとなる重要な選択肢の一つです。
自分のペースで少しずつステップアップできる環境が整っているため、ご本人やご家族にとっても心強い支援となります。
📝関連記事はこちら
知的障害のある方の才能が開花!自分らしい働き方ができるB型事業所選びとは
就労継続支援B型とは何か?対象者・メリット・利用方法まで徹底解説!
【初心者向け】就労継続支援B型とは?制度の概要と失敗しない選び方ガイド
知的障害のある方がB型事業所を利用するための「受け入れ条件」とは?
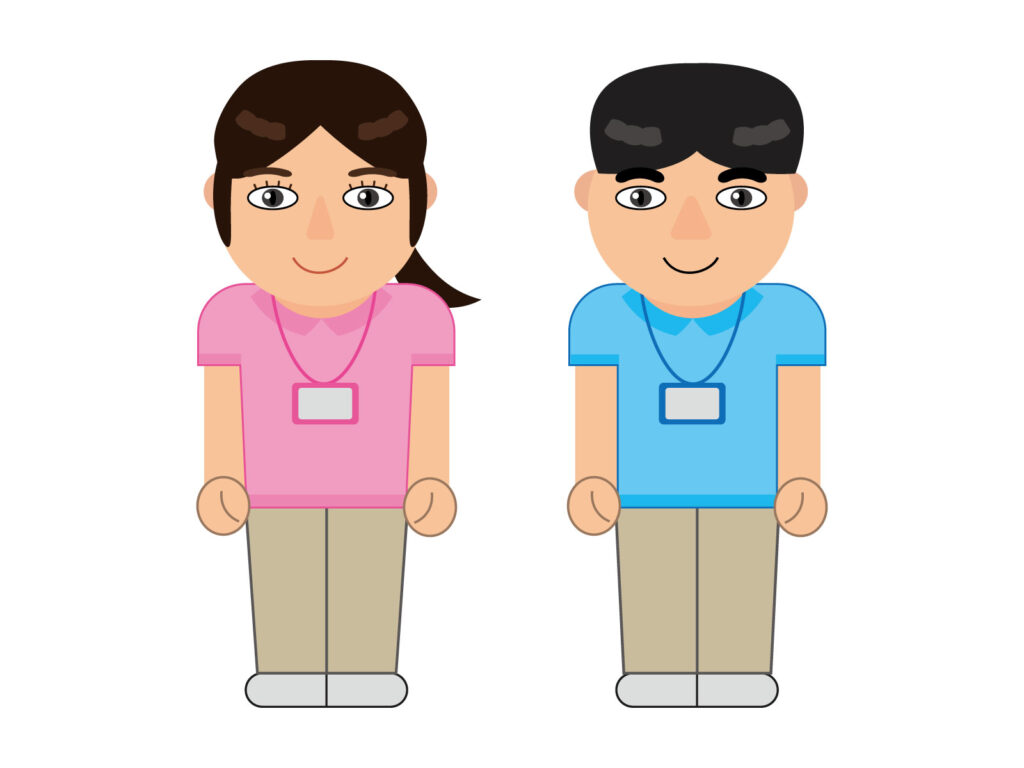
「知的障害があっても、本当にB型事業所を利用できるの?」という疑問に、まず結論からお答えします。
結論:知的障害のある方は、B型事業所の利用可能です。
知的障害のある方は、B型事業所の利用対象者として明確に定められています。
多くのB型事業所が、知的障害のある方を積極的に受け入れており、その特性に配慮した支援体制を整えています。
厚生労働省が定めるB型事業所の対象者は、具体的に以下のような方々です。
厚生労働省が定めるB型事業所の対象者は、具体的に以下のような方々です。



アセスメントとは?
アセスメントとは、ある対象の状態や特性を評価・分析することを指します。
就労継続支援B型の分野では、利用者の能力や適性、課題を把握し、最適な支援方法を決めるために行われます。
■あなたも対象かも?具体的な3つの受け入れ条件をチェック
B型事業所の利用を検討する際、主に以下の3つの条件を満たしているかどうかが一つの目安となります。
条件1:年齢が原則18歳以上であること
B型事業所は、原則として18歳以上の障害のある方が対象です。
高校を卒業した後の進路として選ばれることが多くなっています。
※特例として、18歳未満であっても、児童相談所長の意見書などがあれば利用が認められるケースもあります。
条件2:知的障害や精神障害、身体障害、発達障害、難病などがあること
知的障害は、B型事業所の対象となる障害の一つです。
この場合、障害の程度(軽度・中度・重度)は問われません。
大切なのは「障害があること」であり、その証明として療育手帳や医師の診断書などが用いられます。
条件3:以下のいずれかに当てはまること
年齢と障害の条件に加え、現在の状況が以下のいずれかに当てはまる必要があります。
- 一般企業での就労が難しいと感じている
- 過去に就職活動をしたが、採用に結びつかなかった。
- 企業で働いた経験はあるが、人間関係や作業ペースが合わずに離職してしまった。
- 年齢や体力の面で、長時間働くことに不安がある
- 就労移行支援を利用したが、B型事業所の利用が適していると判断された
- 特別支援学校を卒業後、すぐに就職するのではなく、まずは働くことに慣れる場所を探している
これらの条件は「働く意欲はあるけれど、様々な理由で一般就労が難しい方」を支援するためのものです。
ご自身やご家族がどれかに当てはまるようであれば、B型事業所の利用を具体的に検討してみましょう。
📝関連記事はこちら
就労継続支援B型事業所はどんな人が対象?自分に合った支援を見つけよう!
【就労継続支援B型とは?】仕事内容や作業内容をわかりやすく解説!
【知らないと損!】就労継続支援B型は「手帳なし」で利用OK!受給者証があれば働き方改革が始まる!
軽度知的障害があっても安心して働ける!就労継続支援B型で自分らしい働き方を実現しよう
中等度知的障害でも大丈夫!就労継続支援B型で自分らしく働く方法
【重度知的障害でも働ける!】就労継続支援B型事業所で安心して働く方法とは?
「療育手帳」は絶対に必要?手帳がない場合の利用方法

B型事業所の利用を考える上で、多くの方が気にされるのが「療育手帳(愛の手帳など、自治体により名称が異なる)」の有無です。
療育手帳の役割とは?
療育手帳は、知的障害があることを公的に証明するものです。
そのため、療育手帳を持っていると、B型事業所の利用申請手続きが非常にスムーズに進みます。
障害福祉サービスの利用申請において、障害の状況を客観的に示すための重要な書類となるからです。
■手帳がなくても利用できるケースはあります!
「療育手帳を持っていないと、B型事業所は利用できないの?」と心配されるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
療育手帳がなくても、以下の方法でB型事業所を利用できる可能性があります。
- 医師の診断書や意見書
- 知的障害があることを証明する医師の診断書や、B型事業所の利用が適しているという内容の意見書があれば、手帳の代わりとして認められる場合があります。
- 障害年金の受給証明
- 知的障害を理由に障害年金を受給している場合、その受給者証が証明になることもあります。
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 知的障害に加えて精神障害がある場合など、この受給者証が利用できるケースもあります。
重要なのは、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談してみることです。
専門の相談員が、個々の状況に合わせて必要な書類や手続きの方法を丁寧に教えてくれます。「手帳がないから…」と諦める前に、ぜひ一度、専門機関のドアを叩いてみてください。
安心してください!B型事業所の利用開始までの5つのステップ

「条件は分かったけど、実際にどう動けばいいの?」という方のために、相談から利用開始までの流れを5つのステップで解説します。
この流れを知っておけば、安心して手続きを進めることができます。
- ステップ1:相談する(市区町村の窓口・相談支援事業所)
- まず最初のスタート地点は「相談」です。
お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口、もしくは「相談支援事業所」に連絡を取りましょう。
相談支援事業所とは、障害のある方やご家族の相談に乗り、必要なサービスを受けられるように計画を立ててくれる専門機関です。
どこに相談すれば良いか分からない場合は、まず市区町村の窓口で相談支援事業所を紹介してもらうのが良いでしょう。

- ステップ2:事業所の見学・体験利用
- 相談支援専門員などと相談しながら、興味のあるB型事業所をいくつかピックアップし、見学に行きます。
事業所の雰囲気、作業内容、スタッフや他の利用者さんの様子などを自分の目で確かめることが非常に重要です。
多くの事業所では、半日~数日間の「体験利用」も可能です。
実際に作業を体験することで、「自分に合っているか」「無理なく通えそうか」を判断できます。

- ステップ3:「サービス等利用計画(案)」の作成
- 利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口でサービスの利用申請を行います。
この際、サービスを利用するには、
「どんなふうにサービスを使っていきたいか」
をまとめた「サービス等利用計画案」が必要になります。
この計画は、自治体から認められた相談支援事業所の専門スタッフが一緒に考えて作ってくれます。
また、ご本人やご家族、支援している人が自分たちで作る(セルフプラン)こともできます。

- ステップ4:「障害福祉サービス受給者証」の申請・交付
- ステップ3で作成した計画案や、その他必要な書類(申請書、療育手帳や診断書など)を市区町村の窓口に提出し、「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」の交付を申請します。
市区町村による審査が行われ、利用が決定すると、自宅に受給者証が郵送されてきます。
これで、正式にB型事業所のサービスを利用する権利が得られたことになります。

- ステップ5:利用契約と受け入れ開始
- 受給者証が手元に届いたら、利用したいB型事業所と直接「利用契約」を結びます。
契約内容(利用日、時間、工賃のルールなど)をよく確認し、納得した上で契約しましょう。
契約が完了すれば、いよいよB型事業所の利用スタートです!

知的障害のある方が「自分に合う」B型事業所を選ぶ3つのポイント

受け入れ条件をクリアし、無事に利用を開始できても、「なんだか合わない…」となってしまっては意味がありません。
ミスマッチを防ぎ、長く安心して通い続けるために、事業所を選ぶ際には以下の3つのポイントを意識してみてください。
ポイント1:作業内容が本人の興味や特性に合っているか
B型事業所の作業内容は多岐にわたります。
本人の「好き」「得意」に繋がる作業内容か、あるいは「これならできそう」と思えるものかを確認しましょう。
- 軽作業系: 部品組立、検品、袋詰め、シール貼りなど(手先が器用、コツコツ作業が好き)
- PC作業系: データ入力、簡単な文字起こし、アンケート集計など(PC操作に興味がある)
- 創作活動系: アクセサリー作り、木工、陶芸、絵画など(ものづくりが好き、表現することが好き)
- 食品加工・農業系: パンやお菓子の製造、野菜の栽培・販売など(身体を動かすことが好き)
見学や体験利用の際に、本人がどのような表情で作業に取り組んでいるかを観察することが大切です。
ポイント2:支援体制や事業所の雰囲気は安心できるか
知的障害のある方への支援は、専門的な知識と経験が求められます。
スタッフの専門性や人柄は非常に重要です。
- スタッフは優しく、分かりやすく話してくれるか?
- 困った時にすぐに相談できる雰囲気か?
- 本人の特性(こだわり、パニックへの対応など)を理解し、配慮してくれそうか?
- 他の利用者さんたちが落ち着いて過ごしているか?
事業所全体の「空気感」が本人に合うかどうかは、居心地の良さに直結します。
ご家族だけでなく、ぜひご本人にも「ここの雰囲気、どう思う?」と感想を聞いてみてください。
ポイント3:通いやすさや工賃などの物理的な条件
長く通うためには、現実的な条件も無視できません。
- 場所とアクセス: 自宅から無理なく通える距離か?送迎サービスの有無は?
- 利用時間: 1日の利用時間や週の利用日数は、本人の体力に合っているか?
- 工賃の水準: 工賃は事業所によって異なります。目標とする金額や支払い方法などを確認しておきましょう。
- 昼食の提供: お弁当持参か、給食やお弁当の注文が可能かなども、日々の負担に関わるポイントです。
📝関連記事はこちら
就労継続支援B型事業所の選び方完全ガイド|失敗しない8つのポイントと就労移行支援との徹底比較
就労継続支援B型の工賃・収入ガイド|働き方と生活の安定を徹底解説
就労継続支援B型で工賃アップを目指す!高い工賃を実現する方法と課題
【就労継続支援B型】仕事探しのお悩みを解決!あなたに合った働き方を見つける方法
【Q&A】B型事業所と知的障害に関するよくある質問

-
A型事業所や就労移行支援と、どうちがうの?
-
一番のちがいは「お給料がもらえるかどうか」です。
- A型事業所は、会社と働く約束(雇用契約)をして、最低限のお給料がもらえます。
ある程度、安定して働ける人が対象です。 - B型事業所は、雇用契約を結ばずに、自分のペースで作業して、その成果に応じて「工賃(こうちん)」というお金がもらえます。
- 就労移行支援は、ふつうの会社に就職するための「練習」をする場所です。
使える期間は基本的に2年間と決まっています。
お給料はありません。
- A型事業所は、会社と働く約束(雇用契約)をして、最低限のお給料がもらえます。
-
親や家族が手続きを代わりにしてもいいの?
-
はい、大丈夫です。
書類の作成や役所とのやりとりなど、家族が手伝うことはよくあります。
大切なところ(見学や契約など)は、ご本人が一緒に行くことが多いです。
-
B型事業所ではどれくらいのお金がもらえるの?
-
平均工賃は約27,460円(厚生労働省調べ:令和6年度)
でも、これは「平均」なので、人によってかなり違います。
通う日数や時間、作業の内容などで、月に数千円の人もいれば、もっともらっている人もいます。見学のときに、くわしく聞いてみると安心です。
まとめ:B型事業所で新たな一歩を。
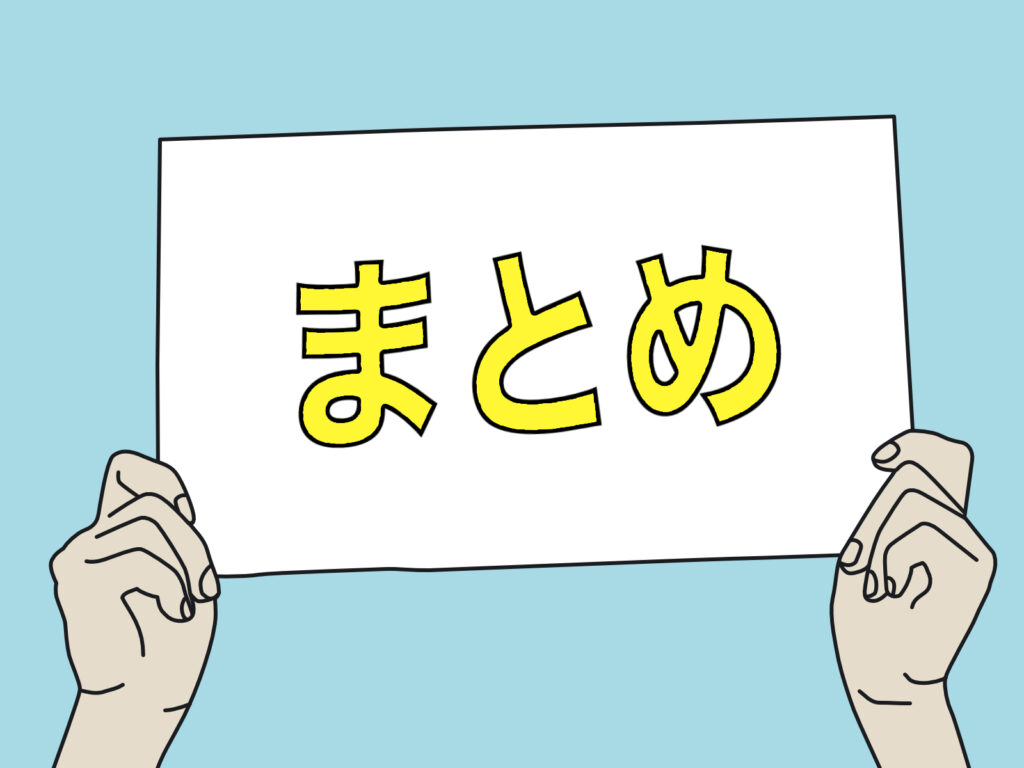
今回は、知的障害のある方が就労継続支援B型事業所を利用するための受け入れ条件を中心に、利用方法や事業所の選び方について詳しく解説しました。
- 知的障害のある方は、B型事業所の利用対象者です。
- 療育手帳がなくても、医師の診断書などで利用できる場合があります。
- 利用には「相談→見学→計画作成→申請→契約」というステップがあります。
- 「作業内容」「支援体制」「通いやすさ」を基準に、本人に合う事業所を選びましょう。
B型事業所は、知的障害のある方が社会とつながり、自分の力を発揮できる素晴らしい場所です。この記事が、皆さまの不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
まずは、地域の相談窓口に相談してみてください。
ちょっとしたきっかけが、これからの新しい一歩につながるかもしれません。
📝 参考リンク(外部)
就労継続支援B型事業所一覧 – 障がい者就労支援情報~全国版~

京都市伏見区にお住まいの皆様へ。
就労継続支援B型事業所「ふじのもり笑店」は、「自分らしく働きたい」という気持ちを大切にする、あなたのための場所です。
就労継続支援の制度や特徴はもちろん、利用の対象となる方、そして利用にあたっての疑問など、皆様にとって役立つ情報を丁寧にご紹介しております。
「まずは少しずつ」「自分のペースで続けたい」
そんな思いをお持ちの京都市伏見区の皆様にも、安心して通っていただける温かい環境をご用意しています。利用者様一人ひとりの「やってみたい」を尊重し、それぞれのペースに合わせた働き方をサポートいたします。
対象となる方について
京都市伏見区にお住まいで、知的障害、精神障害、身体障害、発達障害などをお持ちの方で、一般企業での就労に不安がある方、または就労移行支援事業などを利用したが就労に結びつかなかった方などが対象となります。
お仕事内容について
京都市伏見区の「ふじのもり笑店」では、利用者様の多様なニーズに合わせて、パソコンやスマートフォンを使った様々なお仕事をご用意しています。ご自身のスキルや興味に合わせて、無理なく取り組める作業がきっと見つかります。
在宅ワークも可能!
お仕事内容によっては、ご自宅にいながら働く「在宅ワーク」も可能です。
通所が難しい方でも、社会との繋がりを持ちながら、ご自身のペースで働くことができます。
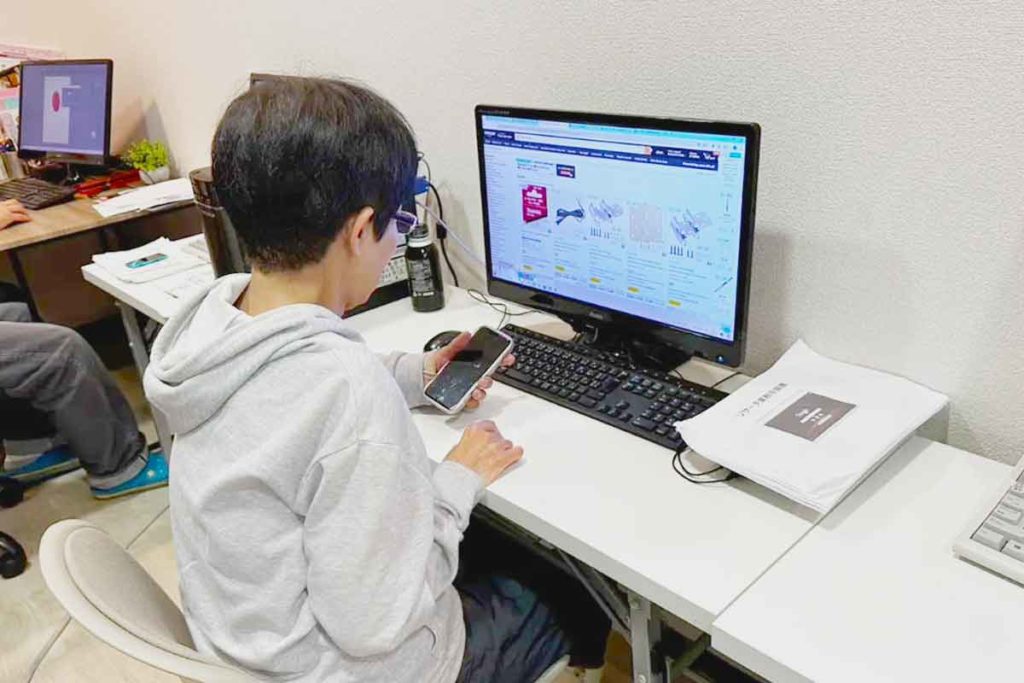
※当事業所では内職の在宅は行っておりません。
「もしかしたら、自分にもできるかも!」
そう感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたが「自分らしく働ける」ためのサポートがここにあります。
安心できる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

どんなことでもお気軽にご相談ください。
スタッフが一人ひとり丁寧に対応させていただきます。


事業所のご案内
🏢 就労継続支援B型事業所 ふじのもり笑店(旧たきがわ笑店)
📮 住所
〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町839-14
ソフトウェーブビル3階
📞 電話番号
075-644-4815
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・祝日除く)
📧 メール
infoshoten-group.com
🌐 公式サイト(HP)
📱 SNS
🚶♂️ アクセス
京阪本線「藤森駅」西口より徒歩3分
ソフトウェーブビルのエレベーターで3階までお越しください。
🏢就労継続支援B型事業所 ふるかわばし笑店
📮 住所
〒571-0030
大阪府門真市末広町1番7号
末広ビル2階(旧松井ビル)
📞 電話番号
050-1506-9415
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚶♂️ アクセス
京阪本線「古川橋駅」より線路沿いに東へ徒歩4分
末広ビル(旧松井ビル)階段で2階までお越しください。

📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)
🏢就労継続支援B型事業所 たけだ笑店
📮 住所
〒612-0028
京都府京都市伏見区竹田段川原町269番地
📞 電話番号
050-1113-9161
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚃 アクセス
京都市営地下鉄・近鉄「竹田駅」北口より徒歩3分
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)


