知的障害のある方の「働く」を支える!就労継続支援B型事業所のサポート体制と選び方ガイド
知的障害のあるご家族の「働く」について、「うちの子でも安心して働ける場所はあるだろうか?」「どんなサポートを受けられるんだろう?」といった不安や疑問をお持ちではありませんか。
その選択肢の一つが「就労継続支援B型事業所」です。
しかし、名前は聞いたことがあっても、具体的にどのような場所で、特に知的障害のある方に対してどんなサポート体制が整っているのか、わからないことも多いでしょう。
この記事では、知的障害のある方とそのご家族が安心して一歩を踏み出せるよう、就労継続支援B型の基本的な情報から、最も気になる「サポート体制」、具体的な仕事内容、そして自分に合った事業所の選び方まで、必要なことをギュッとまとめて、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、就労継続支援B型が知的障害のある方にとって、いかに心強く、可能性を広げる場所であるかがお分かりいただけるはずです。
就労継続支援B型事業所とは?

まず、基本から確認しましょう。
就労継続支援B型事業所(以下B型事業所)とは、障害や難病のある方が、自分のペースで働きながら、社会参加を目指すための福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づいて運営されており、全国に多くの事業所があります。
企業などと雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」とは異なり、B型事業所は雇用契約を結ばずに利用します。
そのため、体調や特性に合わせて週1日や1日数時間からでも利用しやすく、「働く」ことに慣れるための第一歩として最適な場所と言えます。
特に知的障害のある方にとっては、みんな同じルールで働く一般就労よりも、一人ひとりの特性や能力に合わせてサポートを受けられるB型事業所が、強みを発揮しやすい環境となるケースが多くあります。
📝関連記事はこちら
就労継続支援B型とは何か?対象者・メリット・利用方法まで徹底解説!
【初心者向け】就労継続支援B型とは?制度の概要と失敗しない選び方ガイド
「自分らしく働きたい」知的障害のある方を応援!就労継続支援B型とは?
知的障害のある方への具体的なサポート体制とは?

「サポート体制」と一言で言っても、具体的にどんな支援を受けられるのでしょうか?
知的障害のある方が安心して活動するために、多くのB型事業所では以下のような多角的なサポート体制を整えています。
① 一人ひとりの「得意」と「苦手」に合わせた個別支援計画
B型事業所でのサポートの根幹となるのが「個別支援計画」です。
これは、利用者さん一人ひとりの障害特性、得意なこと、苦手なこと、そして「こうなりたい」という目標を丁寧にヒアリングし、作成するオーダーメイドの支援プランです。
<個別支援計画で考えることの例>
- 得意な作業: 手先が器用、集中力が高い、単純作業が好き など
- 苦手なこと: 大きな音が苦手、複数の指示を一度に覚えるのが難しい、人とのコミュニケーション など
- 本人の希望: 「〇〇な作業がしてみたい」「工賃で△△を買いたい」「友達を作りたい」など
- ご家族の希望: 「生活リズムを整えてほしい」「日中の居場所として安心して通わせたい」など
この計画に基づき、スタッフは「どの作業が向いているか」「どのような声かけが分かりやすいか」「どんな環境設定が必要か」などを考え、日々の支援に活かします。
計画は定期的に見直され、その時々の状況に合わせて更新されるため、常に最適なサポートを受けることができます。
② 「見てわかる」「やってみせる」丁寧な作業指導
知的障害のある方にとって、口頭だけの長い説明は理解が難しい場合があります。
そのため、多くの事業所では「見てわかる」支援を徹底しています。
- 作業手順の図解・マニュアル化: 写真やイラストを使って、作業の手順を壁に掲示したり、個別のファイルを用意したりします。
- 見本(サンプル)の提示: 完成形の見本を常にそばに置き、いつでも確認できるようにします。
- スタッフによる実演: まずスタッフが実演し次に一緒に行い、最終的に一人でできるように、段階を踏んで指導します。
- 補助工具の活用: 作業を簡単・正確にするための補助工具(例えば、決まった長さに切るためのガイドや、穴を開ける位置を示す型など)を用意し、失敗を減らす工夫をします。
このような視覚的な支援とスモールステップでの指導により、抽象的な概念の理解が苦手な方でも、安心して作業に取り組むことができます。
③ コミュニケーションと人間関係のサポート
「他の利用者さんと上手くやれるか心配」という声は、ご家族から非常によく聞かれます。
B型事業所は、社会性を育む場でもあります。
- SST(ソーシャルスキルトレーニング): 挨拶の仕方、報告・連絡・相談の方法、適切な断り方など、対人関係のスキルを学ぶ機会を設けている事業所もあります。
- 気持ちを伝えるツールの活用: 言葉で表現するのが苦手な方のために、絵カードやコミュニケーションボードを使って「手伝ってほしい」「休憩したい」といった意思を伝えられるように工夫します。
- スタッフの仲介: 利用者さん同士でトラブルが起きた際には、スタッフが間に入り、双方の気持ちを聞きながら解決に導きます。
一方的にどちらかが悪いと決めつけるのではなく、お互いが安心して過ごせるためのルールを一緒に考えます。
④ 生活リズムや体調管理の支援
安定して通所するためには、生活リズムの確立が不可欠です。
- 通所リズムの相談: 「まずは週2日の午前中だけ」から始め、体力や意欲に応じて徐々に日数や時間を増やしていくなど、柔軟な対応が可能です。
- 健康管理のサポート: 朝の会で体調を確認したり、服薬管理の補助を行ったり、定期的な健康相談を実施したりします。
ご家族や医療機関との連携も密に行い、利用者さんの心身の健康を支えます。 - 休憩の促し: 集中しすぎてしまう方には適度な休憩を促し、疲れが溜まりやすい方にはこまめな休息時間を設定するなど、個々のペースを尊重します。
📝関連記事はこちら
就労継続支援B型の人間関係トラブルを解決する方法|利用者・職員が安心して働くためにできること
体調や人間関係に不安があっても大丈夫!就労継続支援B型の精神的サポートで「働く」を実現
知的障害のある方が活躍できる!B型事業所の具体的な仕事内容

B型事業所の仕事内容はさまざまです。
ここでは、知的障害のある方が自分の特性を活かして活躍しやすい作業例をいくつかご紹介します。
- 軽作業(コツコツ系)
- 例: 部品組立、検品、シール貼り、箱折り、袋詰め、DM封入など
- 向いている方: 決まった手順を繰り返す作業が得意な方、手先が器用な方、一人で黙々と集中したい方。
- PC作業(デジタル系)
- 例: データ入力、文字起こし、簡単な画像加工、アンケート集計など
- 向いている方: パソコン操作が好きな方、タイピングが得意な方、正確性が求められる作業にやりがいを感じる方。
- 創作・製造(クリエイティブ系)
- 例: パン・お菓子の製造販売、手工芸品(アクセサリー、布小物など)の制作、アート作品の制作など
- 向いている方: ものづくりが好きな方、自分のアイデアや感性を形にしたい方。事業所オリジナルの商品作りに関われることもあります。
- 農作業・屋外作業(アクティブ系)
- 例: 野菜の栽培・収穫、公園や施設の清掃、ポスティングなど
- 向いている方: 体を動かすのが好きな方、自然の中で働くのが好きな方。季節を感じながら働けるのが魅力です。
事業所によって請け負っている仕事は様々です。
見学の際に、どのような仕事があるのか、自分(またはご家族)が興味を持てそうな作業はあるかを確認することが重要です。
📝関連記事はこちら
【就労継続支援B型とは?】仕事内容や作業内容をわかりやすく解説!
就労継続支援B型事業所はどんな人が対象?自分に合った支援を見つけよう!
安心できるB型事業所を見つけるためのチェックポイント5選

数ある事業所の中から、本人に合った場所を見つけるためにはどうすれば良いのでしょうか。
見学や体験利用の際に、ぜひ確認してほしい5つのポイントをご紹介します。
① スタッフの専門性と人柄・雰囲気
スタッフは、日々の支援の中心となる最も重要な存在です。社会福祉士や精神保健福祉士、作業療法士などの専門資格を持つスタッフがいるかどうかも一つの指標ですが、それ以上に「人柄」や「利用者さんへの接し方」をよく観察しましょう。
- スタッフは利用者さん一人ひとりの名前を呼び、目を見て話していますか?
- 指示や説明は丁寧で分かりやすいですか?
- 利用者さんが困っている時に、すぐに気づいて声をかけていますか?
- 事業所全体の雰囲気は明るく、穏やかですか?
② 個別支援計画を一緒に作ってくれるか
前述の「個別支援計画」を、本人や家族の意見をしっかり聞いた上で作成してくれるかどうかが重要です。
一方的に事業所の方針を押し付けるのではなく、対話を重視し、パートナーとして支援してくれる姿勢があるかを確認しましょう。
③ 事業所の環境設備と安全管理
知的障害のある方の中には、感覚が過敏な方もいらっしゃいます。
- 環境: 照明が明るすぎないか、騒音はどの程度か、パーソナルスペースは確保されているかなど、本人が落ち着いて過ごせる環境かを確認します。
- 安全: 作業スペースは整理整頓されているか、危険な工具の管理は徹底されているか、災害時の避難経路は確保されているかなど、安全への配慮も大切なポイントです。
④ 見学・体験利用の内容
ほとんどの事業所で見学や体験利用が可能です。
ぜひ一度だけでなく、複数回体験してみることをお勧めします。
体験利用では、実際の作業を少しやらせてもらい、一日の流れを体験することで、向き不向きや雰囲気との相性がより明確になります。
⑤ 利用者さんの表情や様子
実際にその事業所を利用している方々の表情や様子は、その場所の良さを何よりもはっきりと伝えてくれます。
利用者さんたちがリラックスして、楽しそうに活動しているか、自分の役割に誇りを持って取り組んでいるかを見てみましょう。
📝関連記事はこちら
【知的障害×就労継続支援B型】自分に合った事業所の選び方|後悔しないための完全ガイド
【知的障害×就労支援】B型事業所ってどんなところ? 仕事内容から選び方までやさしく解説
利用開始までの流れをわかりやすく解説
以下は一般的な流れです。ぜひご参考にしてください。
- Step1:相談する
- まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談します。
自分の状況を話し、B型事業所の利用を検討していることを伝えましょう。

- Step2:事業所を探し、見学・体験利用をする
- 相談機関から情報を得たり、インターネットで探したりして、気になる事業所を見つけたら、電話やメールで見学・体験の申し込みをします。
複数の事業所を比較検討するのがおすすめです。

- Step3:利用申請を行う
- 利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口でサービスの利用申請を行います。
この際、サービスを利用するには、
「どんなふうにサービスを使っていきたいか」
をまとめた「サービス等利用計画案」が必要になります。
この計画は、自治体から認められた相談支援事業所の専門スタッフが一緒に考えて作ってくれます。
また、ご本人やご家族、支援している人が自分たちで作る(セルフプラン)こともできます。
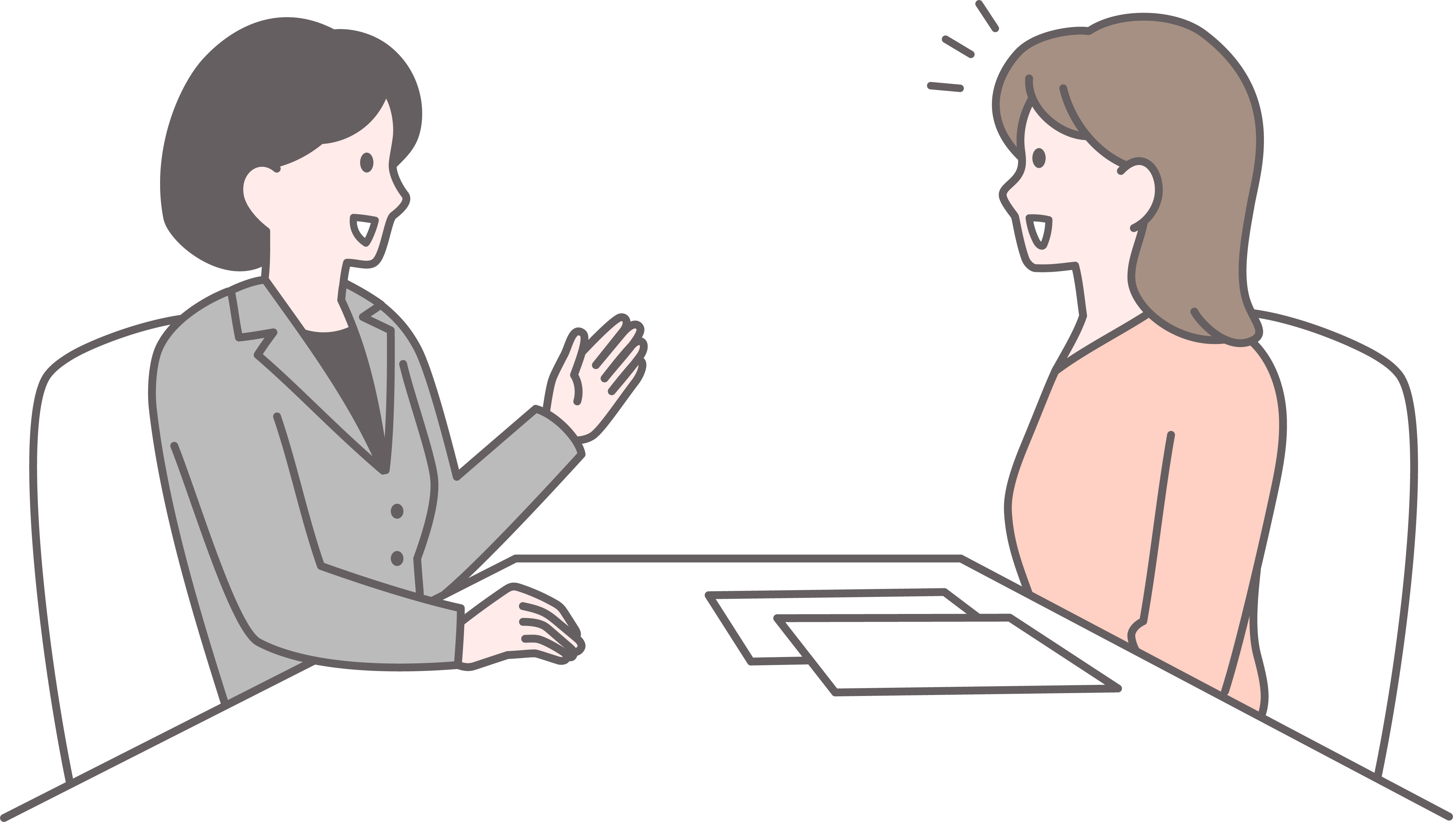
- Step4:支給決定と「障害福祉サービス受給者証」の交付
- 市区町村による審査を経て、サービスの利用が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
これがB型事業所を利用するための許可証のようなものです。

- Step5:事業所との契約・利用開始
- 受給者証を持って事業所へ行き、利用契約を結びます。
契約内容をよく確認し、納得できたら利用開始です。

よくある質問(FAQ)

知的障害のある方のご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
-
知的障害の程度が重いのですが、利用できますか?
-
はい、利用できる可能性は十分にあります。
B型事業所は、障害の程度に関わらず、働く意欲のある方を幅広く受け入れています。
事業所によっては、重度の障害がある方向けの支援に特化している場所もあります。
まずは諦めずに、相談支援事業所や気になる事業所に問い合わせてみてください。
-
人間関係が苦手で、トラブルを起こさないか心配です。
-
そのような不安を抱える方は少なくありません。
B型事業所のスタッフは、ご本人の特性を理解した上で、他者との関わり方を一緒に考え、必要に応じて仲介に入ります。
個別作業が多い事業所を選ぶなど、環境面で配慮することも可能です。
-
工賃はどれくらいもらえますか?
-
工賃は、生産活動による収益から支払われるため、事業所や作業内容、個人の作業時間によって異なります。
雇用契約を結ばないため最低賃金の適用はなく、令和6年度の全国平均工賃(月額)は、23,053円(厚生労働省調べ)ですが、これはあくまで平均値です。
工賃アップを目標に支援してくれる事業所も増えています。
金額だけでなく、工賃が「自分の頑張りの証」として本人の意欲に繋がることが大切です。
-
家族はどのように関わればよいですか?
-
ご家族との連携は、支援において非常に重要です。
事業所のスタッフと定期的に連絡を取り合い、ご家庭での様子と事業所での様子を情報共有することが、より良いサポートに繋がります。
面談の機会などを活用し、不安なことや希望を積極的に伝えていきましょう。
ご家族だけで抱え込まず、事業所を「一緒に支えるチーム」として頼ってください。
📝関連記事はこちら
就労継続支援B型の工賃・収入ガイド|働き方と生活の安定を徹底解説
就労継続支援B型で工賃アップを目指す!高い工賃を実現する方法と課題
【親御さん必見】知的障害のある子どもの就労継続支援B型とは?親ができる支援・サポートの方法を解説
軽度知的障害があっても安心して働ける!就労継続支援B型で自分らしい働き方を実現しよう
中等度知的障害でも大丈夫!就労継続支援B型で自分らしく働く方法
【重度知的障害でも働ける!】就労継続支援B型事業所で安心して働く方法とは?
まとめ:一人ひとりに寄り添うサポートで、「働く喜び」を見つけよう
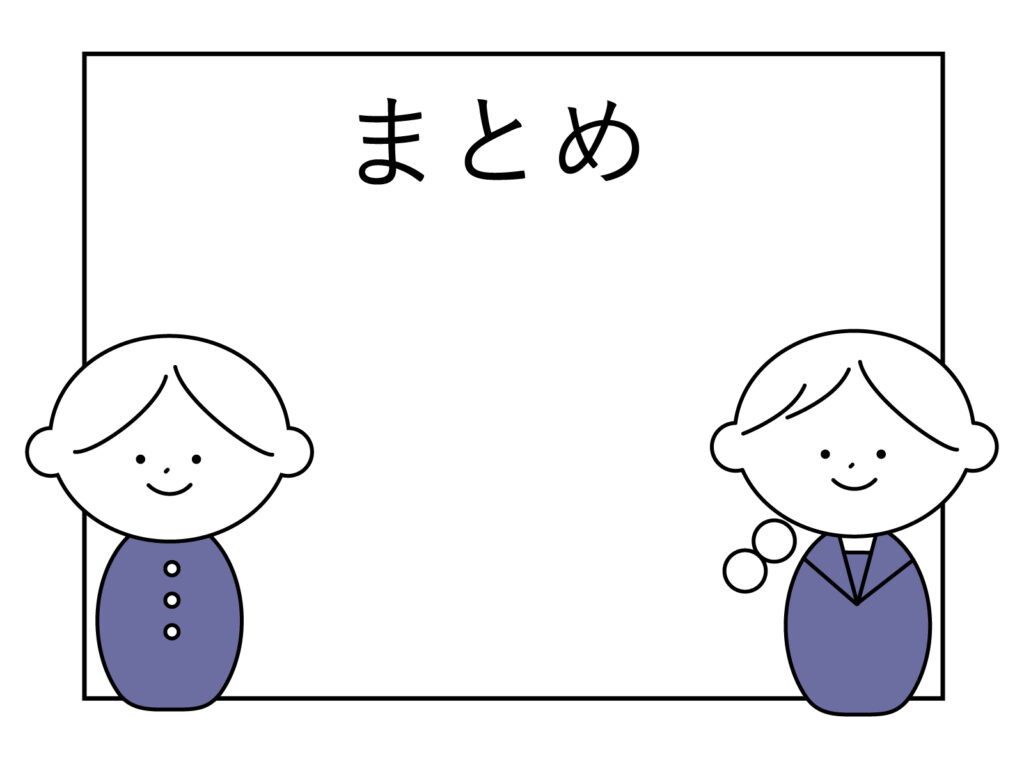
就労継続支援B型事業所は、単に作業をする場所ではありません。
知的障害のある方一人ひとりの特性と可能性に光を当て、「自分にもできることがある」「誰かの役に立っている」という自信と働く喜びを育む場所です。
今回ご紹介したように、B型事業所には、知的障害のある方が安心して力を発揮できるよう、個別支援計画を軸とした手厚いサポート体制が整っています。
この記事が、ご本人とご家族にとって、未来への希望ある一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
まずは勇気を出して、お近くの相談窓口や事業所に「見学したいのですが」と連絡を取ることから始めてみませんか。
そこには、温かく、頼りになるサポートが待っているはずです。
📝 参考リンク(外部)
就労継続支援B型事業所一覧 – 障がい者就労支援情報~全国版~

京都市伏見区にお住まいの皆様へ。
就労継続支援B型事業所「ふじのもり笑店」は、「自分らしく働きたい」という気持ちを大切にする、あなたのための場所です。
就労継続支援の制度や特徴はもちろん、利用の対象となる方、そして利用にあたっての疑問など、皆様にとって役立つ情報を丁寧にご紹介しております。
「まずは少しずつ」「自分のペースで続けたい」
そんな思いをお持ちの京都市伏見区の皆様にも、安心して通っていただける温かい環境をご用意しています。利用者様一人ひとりの「やってみたい」を尊重し、それぞれのペースに合わせた働き方をサポートいたします。
対象となる方について
京都市伏見区にお住まいで、知的障害、精神障害、身体障害、発達障害などをお持ちの方で、一般企業での就労に不安がある方、または就労移行支援事業などを利用したが就労に結びつかなかった方などが対象となります。
お仕事内容について
京都市伏見区の「ふじのもり笑店」では、利用者様の多様なニーズに合わせて、パソコンやスマートフォンを使った様々なお仕事をご用意しています。ご自身のスキルや興味に合わせて、無理なく取り組める作業がきっと見つかります。
在宅ワークも可能!
お仕事内容によっては、ご自宅にいながら働く「在宅ワーク」も可能です。
通所が難しい方でも、社会との繋がりを持ちながら、ご自身のペースで働くことができます。
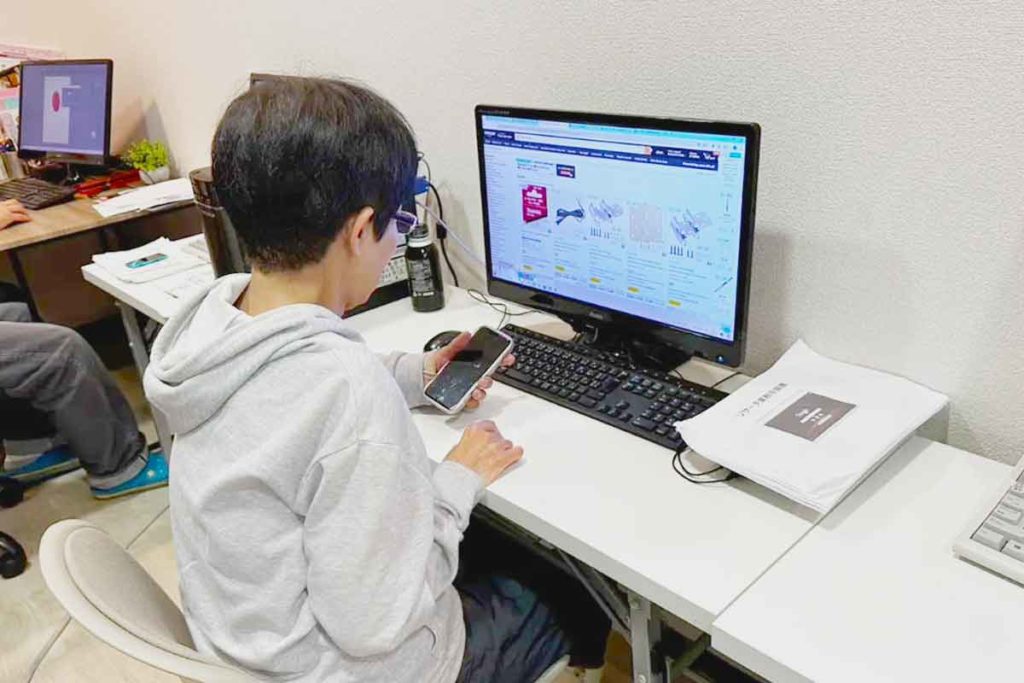
※当事業所では内職の在宅は行っておりません。
「もしかしたら、自分にもできるかも!」
そう感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたが「自分らしく働ける」ためのサポートがここにあります。
安心できる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

どんなことでもお気軽にご相談ください。
スタッフが一人ひとり丁寧に対応させていただきます。


事業所のご案内
🏢 就労継続支援B型事業所 ふじのもり笑店(旧たきがわ笑店)
📮 住所
〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町839-14
ソフトウェーブビル3階
📞 電話番号
075-644-4815
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・祝日除く)
📧 メール
infoshoten-group.com
🌐 公式サイト(HP)
📱 SNS
🚶♂️ アクセス
京阪本線「藤森駅」西口より徒歩3分
ソフトウェーブビルのエレベーターで3階までお越しください。
🏢就労継続支援B型事業所 ふるかわばし笑店
📮 住所
〒571-0030
大阪府門真市末広町1番7号
末広ビル2階(旧松井ビル)
📞 電話番号
050-1506-9415
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚶♂️ アクセス
京阪本線「古川橋駅」より線路沿いに東へ徒歩4分
末広ビル(旧松井ビル)階段で2階までお越しください。

📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)
🏢就労継続支援B型事業所 たけだ笑店
📮 住所
〒612-0028
京都府京都市伏見区竹田段川原町269番地
📞 電話番号
050-1113-9161
🕒 営業時間
9:00~18:00(⼟日休み)
📧 メール
infoshoten-group.com
🚃 アクセス
京都市営地下鉄・近鉄「竹田駅」北口より徒歩3分
📥 受付時間
9:00~18:00(⼟日・休業日除く)


